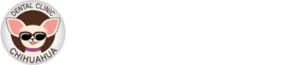For Patients
歯がズキズキ痛む、歯茎が腫れて痛いなどの症状の場合、むし歯や歯周病が疑われます。
むし歯は風邪などと違い、放置しておいても治る病気ではありません。
早めの治療によって、治療時間も痛みも費用も節減できます。
caries

むし歯治療とは
むし歯が進行している場合、悪い部分を早めに除去しなければどんどん悪化します。歯を削る際に痛みが予想される場合は、丁寧に麻酔を行って極力痛みが無いようにいたします。
また、削った部分は詰め物・被せ物でカバーすることも必要です。当クリニックはどの工程にも細かく配慮しながら、出来るだけ苦痛が無いように治療を行っています。
むし歯の進行度・治療法
-
C0

脱灰
歯の一番表面にあるエナメル質が白く濁った状態です。溝の部分が茶色っぽくなることもありますが、見た目にはほとんど変化がありません。
- 治療法
- ブラッシングを丁寧に行えば再石灰化作用により、元の健康な歯質に戻すことが期待できます。
また歯科医院でフッ素塗布を行えば、よりむし歯の進行を防ぐことが可能です。
-
C1

エナメル質のむし歯
酸がエナメル質を溶かし穴が空いています。細菌が内部に進入しているので、ブラッシングやフッ素塗布による再石灰化では根本的な治療に結びつきません。痛みや違和感などの自覚症状もほとんどありません。
- 治療法
- むし歯になっている部分を取り除き、樹脂(コンポジットレジン)を詰めるのが基本的な流れです。
-
C2

象牙質のむし歯
エナメル質のさらに奥にある象牙質まで細菌が進行した状態です。象牙質はエナメル質に比べると柔らかいため、一気にむし歯は拡大します。歯髄(神経)の近くにまで進行していると、冷たい水や甘いお菓子、温かい食事がしみるようになります。
- 治療法
- 麻酔処置後、むし歯を削っていきます。その後に型をとり、詰め物(インレー)を入れていくのが基本的な治療法です。
-
C3

神経のむし歯
象牙質の中にある歯髄も細菌感染しています。歯髄には血管や神経が含まれているため、炎症によって激しい痛みが起こったり、知覚過敏が生じたりします。歯髄炎と呼ばれる症状です。
- 治療法
- 細菌に感染した歯髄を丁寧に取り除く必要があります。これを歯の根の治療(根管治療)と呼び、歯を残すために必要な処置です。神経を取り除くと、歯は割れやすくなるため土台を入れて補強。その後に被せ物(クラウン)をします。
-
C4

歯根のむし歯
歯髄炎を放置すると、どこかの段階で痛みは消失します。これは細菌によって歯の神経が失われたためです。しかし、治ったわけではないので、放置していると根の先に炎症が起こります。最悪のケースでは顎の骨にまで細菌が感染するケースもあります。
- 治療法
- この段階になると、歯を残すことは難しい状況です。
抜歯の後は補綴(ほてつ)治療を行い、歯の機能を回復します。
-

再治療のリスクを下げる治療
むし歯が神経に到達した場合、神経をカバーしている根管という筒状の組織の内部にも感染が起こっています。これを放置すると歯の根で炎症が起こるなどして再治療の必要が出るので、それを防ぐために「根管治療」を行います。
根管は非常に細長く形状が複雑なので、内部の洗浄は難易度が高いのですが、これをおろそかにすると歯を失うことにもなります。当クリニックは患者さまの天然歯を守るため、丁寧に根管治療を行っています。 -

歯を削った後の白い詰め物
むし歯を削った後は詰め物・被せ物を必要とします。その際、「銀歯やプラスチックの歯は見た目の違和感が気になる」という方に向けて、セラミックなどの審美性が高い素材を多数扱っています。
当クリニックでは、最短1日でできるセレックシステムによる詰め物での治療も行っております。
periodontal

歯周病治療とは
「歯周病は高齢者の病気」というイメージを持つ方も多いようですが、実は10代、20代の人でも発症する病気です。ただ、歯周病は時間をかけて進行し、初期には自覚症状が無いことから、中高年になって症状が顕著になる例が多いのです。
歯周病は悪化すると歯を失う原因となりますが、正しい知識と適切なケアで予防できます。また、早期であるほど治療も容易ですから、まずは当クリニックで検診を受けて状況を確認することから始めましょう。
歯周病の進行度・治療法
-
01

歯肉炎
歯肉溝にプラークがたまり歯肉が炎症ではれ、歯肉ポケットになります。まだ、歯根膜(しこんまく)や歯槽骨は破壊されていません。
-
02

軽度歯周炎
歯肉のはれが大きくなり、歯周病菌が歯周組織に侵入し、歯槽骨や歯根膜も破壊されはじめました。ポケットが内部に向かって深くなり、歯周ポケットになっています。プラークや歯石が歯周ポケットに溜まっています。
-
03

中等度歯周炎
炎症がさらに拡大して歯槽骨も歯の根の長さの半分近くまで破壊され、歯がぐらつきはじめます。歯周ポケットもさらに深くなっています。
-
04

重度歯周炎
歯槽骨が半分以上破壊され、歯はぐらぐらです。

全身の様々な病気に
影響を及ぼす歯周病
近年の研究で、歯周病菌はお口の中だけでなく身体の各所に害を及ぼすことがわかってきました。
例えば、傷口から血管に入った歯周病菌は、血流を阻害して脳梗塞や心筋梗塞などの重大な疾患の原因となることがあります。また、肺に侵入すると誤嚥性肺炎を起こすきっかけになりますし、歯周病の炎症反応は糖尿病を悪化させることも報告されています。
ほかにも、歯周病菌は関節リウマチや骨粗しょう症、早産や低体重児出産など、さまざまなリスクを上昇させますから、ぜひお口のケアを向上して菌の生息数を減らしましょう。

早めの予防が肝心
歯周病は歯を失う原因の第1位ですが、予防できる病気でもあります。歯周病は細菌感染症ですから、まずお口の中を清潔に保つことが重要です。そのためには、歯科医院で指導を受けてセルフケアの質を上げること、プロによるクリーニングでセルフケアでは取れない汚れを落とすことが、予防の手段として非常に有効です。